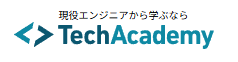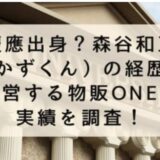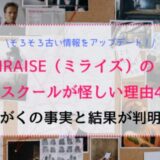AI ONEの広告を見て「なんかきもい」って感じてませんか?
繰り返し出てくる広告を見て違和感を感じたり、胡散臭く感じるのも無理はありません。
特に、強めの演出やクセのある言い回しに抵抗を感じてしまう方は多いはずです。
- 「きもい」と言われる印象の正体や意図を言語化
- 実際に学べる内容やサポート体制を中立的に検証
- 他スクールとの違いや強みを比較
- YouTube動画の内容から、信頼できるかを読み取る

私は、本業でAIツールを活用しながら業務効率を上げてきました。
いくつかのAIスクールを比較検討してきた経験から、
見た目の印象ではなく「中身」に注目する視点を大切にしています。
この記事を読めば、「なんとなくきもい」という感覚に対して、冷静な視点で向き合えるようになります。
広告や演出に振り回されず、自分の目で見て判断できる力が身につくはずです。
迷いや不安を抱えたまま進めないあなたにこそ、役立つ内容になっています。
「きもい」印象の裏にある、意外な狙いや意図
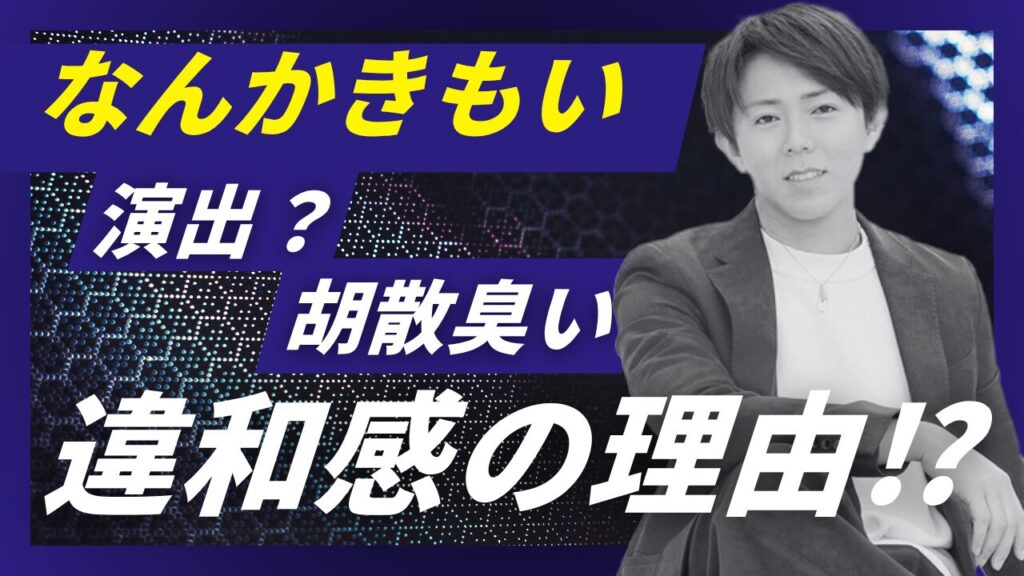
AI ONEの広告を見て「なんかきもい」と感じる人は少なくありません。
強い言葉づかいやクセのある演出に、不安を覚えるのはごく自然な反応です。
実際、SNS上では「またこの広告…」「ちょっと胡散臭いかも」といった声も散見されます。
ただ、その“違和感”には理由があるんです。
広告ではあえてインパクトを重視した演出をすることで、記憶に残りやすくし、印象づける狙いがあります。
特に副業に興味はあるものの、まだ一歩踏み出せていない層に対して、「今動かないと損をする」という危機感を喚起しようとしているのです。
また、広告の印象に影響している要素として、代表・森谷和正氏の“過去の発信スタイル”も一因かもしれません。
本人も28歳の誕生日にXで「月収300万!稼いでない奴は雑魚!」といった尖った発信をしていた過去を振り返り、「敵を作っていた」と反省の気持ちを述べています。
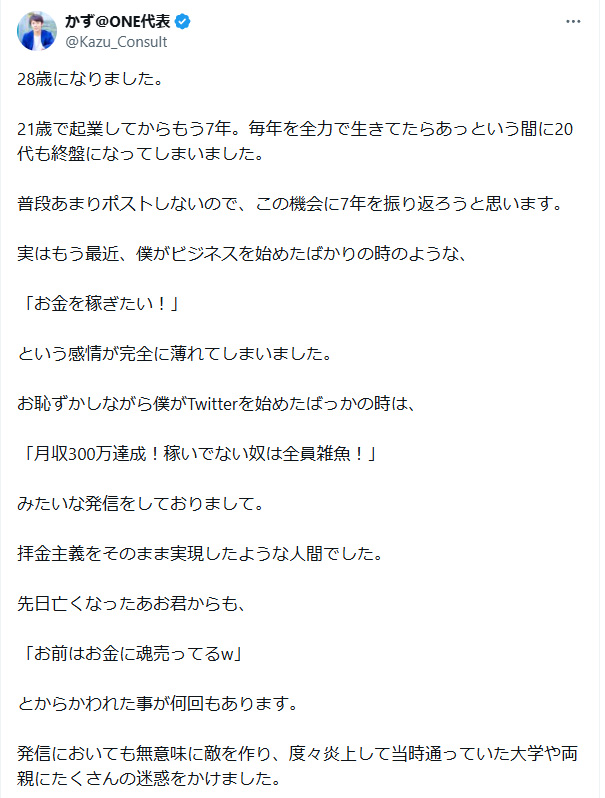

最初は「ちょっときもいかも…」と感じたのが正直なところですが、森谷和正氏が発信スタイルの変化を語っているのを見て、印象が少しやわらぎました。
こうした背景を知ると、派手な演出や過去のキャラに惑わされず、今の取り組みを冷静に見る視点が大切だとわかってきます。
AI ONEは信頼できるサービスなのか検証

広告だけでは本当の中身が見えづらいAI ONEですが、実際の運営や講師、教材の内容、サポート体制までを見ていくと、印象が変わる部分もあります。
ここでは、表面ではわからない実態を一つずつ確認していきます。
運営会社や講師陣に怪しい点はないか

AI ONEは2025年に設立された「株式会社AI ONE」が運営しており、登記情報や代表者の氏名、所在地まで公式に確認できます。
代表の森谷和正氏は、以前に物販スクールを手がけていた経験があり、教育分野での発信歴も長めです。
講師には、AIツールやChatGPTの運用に詳しい人材が起用されており、実名も公表されているため、運営の透明性は高いといえるでしょう。
カリキュラムの内容は実用的か
AI ONEでは、生成AIを使った業務効率化や発信支援をテーマに、ChatGPTや画像生成ツールの使い方を学べる動画教材が用意されています。
プロンプトの基本から実践的な応用までカバーしており、内容は初心者にもわかりやすく設計されています。
100本以上の教材があるため、必要な部分から自由に学べるのもメリットも1つです。
副業や日常業務に役立てたい人にとって、応用の幅が広い内容といえます。
サポート体制や受講環境に不安はないか
サポート体制は、AI ONEの大きな強みの一つです。
LINEオープンチャットを使った質問専用グループや、講師による個別フィードバックも用意されています。
さらに、オンライン勉強会やオフ会も定期的に開催され、学習のモチベーションを保ちやすい環境が整っています。

実は私も「広告の見た目はちょっと強めだけど、内容は意外と実用的だった」と感じた一人です。サポートの様子も想像より丁寧で、学びやすい環境が整っていると感じました。
無期限の無料サポートがつく点も、初心者には安心材料となりますね。
もう少しスクールの内容が知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。
他のAIスクールと比べてわかる、AI ONEの特徴
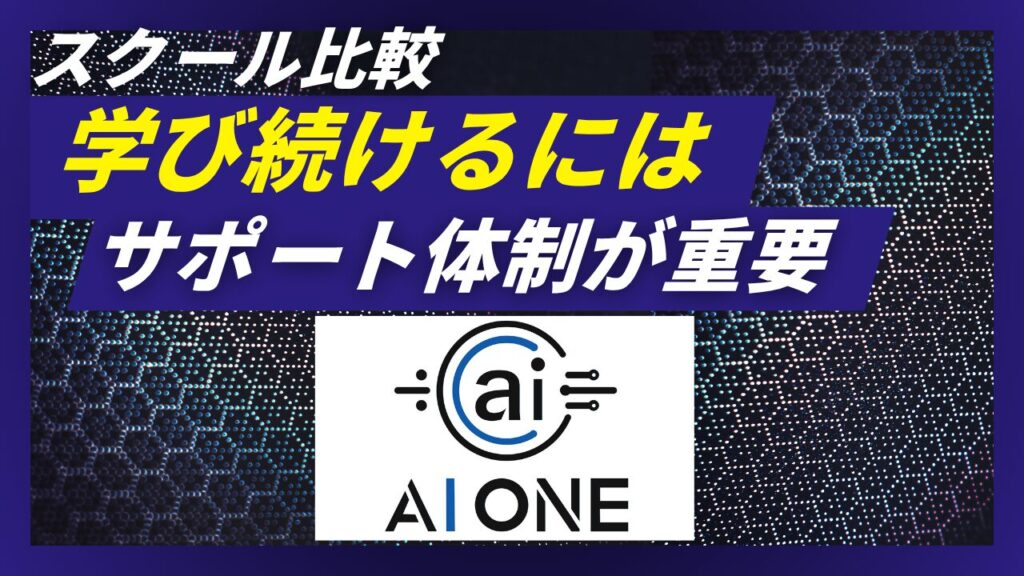
AI ONEは、サポート体制の手厚さが際立っています。
他のAIスクールでは「動画を見て自学自習」が基本のケースも多い中、AI ONEでは質問専用グループやプロンプト共有、Zoom勉強会など、学びを止めない仕組みが豊富に用意されています。
下記は、代表的なオンラインAIスクールと比較した際の特徴です。
Zoomでの質問対応
◎
オンライン勉強会あり
△
一部コースで面談
✕
LINEでの個別サポート
◎
講師対応
✕
✕
講師からの
積極的なフォロー
◎
声かけ・添削・面談
〇
質問への返信あり
△
基本は受け身
教材や
カリキュラムの柔軟性
〇
教材+
オンライン勉強会
〇
テキスト+動画+課題
◎
自習+課題添削
生徒同士
講師との交流
◎
生徒同士+講師
✕
△
バーチャル学習室やSlack
卒業後の
アフターフォロー
◎
無料・無期限
△
有料で延長
△
有料で延長
実際、比較表を見てもわかるように、講師に直接相談できる環境や卒業後の無期限のサポートなど、他スクールと比べても優位な点が多く見られます。
特に「疑問がすぐ解消できる」体制があることで、初心者でも安心して学び続けやすくなっています。

サポートがしっかりしていると、つまずいたときにすぐ立て直せるのが強みですね。
YouTube動画から、発信内容の信頼性をチェック

AI ONE代表のかず氏(森谷和正)のYouTubeでは、広告とは異なる一面が見られます。
実際の動画では、AI活用の実例やノウハウを丁寧に解説しており、情報の信頼性を判断するうえで有益な手がかりになります。
今回紹介するのは【初心者】ガチで使えるChatGPT最強活用術3選です。
日常生活に役立つAI活用術をわかりやすく紹介
YouTubeでは、AIツールを副業だけでなく、日常生活に応用する方法も取り上げています。
例えば、ChatGPTを使って子どもの誕生日に手紙を書いたり、引っ越しの際に不動産会社とのやりとりを効率化する活用法が紹介されていました。
こうした身近な場面での使い方が提示されることで、AIに対するハードルが下がり、初めて触れる人でも「自分にもできそう」と感じやすくなります。

私も動画をきっかけに、メール文の整理にAIを取り入れました。仕事の効率がすごく良くなって、本当に助かっています。
初心者でもすぐ試せる具体例が多い
動画では、難しい専門用語を避け、手順もシンプルに説明されています。
例えば、営業メールをAIで改善したり、SNSの投稿文を整えたりと、すぐに使えるテクニックが満載です。
実際のプロンプト例も画面で見せてくれるため、初心者がそのまま真似できるのも大きな特徴です。
「何から始めていいかわからない」と感じていた人にも、具体的な一歩を示してくれる構成になっています。
見た目の印象と中身のギャップに気づける内容
広告では派手な演出が目立つAI ONEですが、YouTube動画を視聴すると、そのギャップに気づく人も多いはずです。
講師の森谷和正氏は落ち着いた口調で話し、視聴者の目線に立った説明を意識しており、真剣にAIを学んでほしいという姿勢が伝わってきます。
「きもい」「うさんくさい」と感じていた印象が、実際の中身を知れば少しずつ変わる可能性もあるでしょう。
広告とコンテンツにギャップがあるからこそ、実際の発信内容をチェックすることが重要です。

広告には少し抵抗がありましたが、動画で話す姿を見て印象が変わりました。思った以上に丁寧で、誠実さが伝わってきます。
LINE登録して無料でAIを学んでみた!
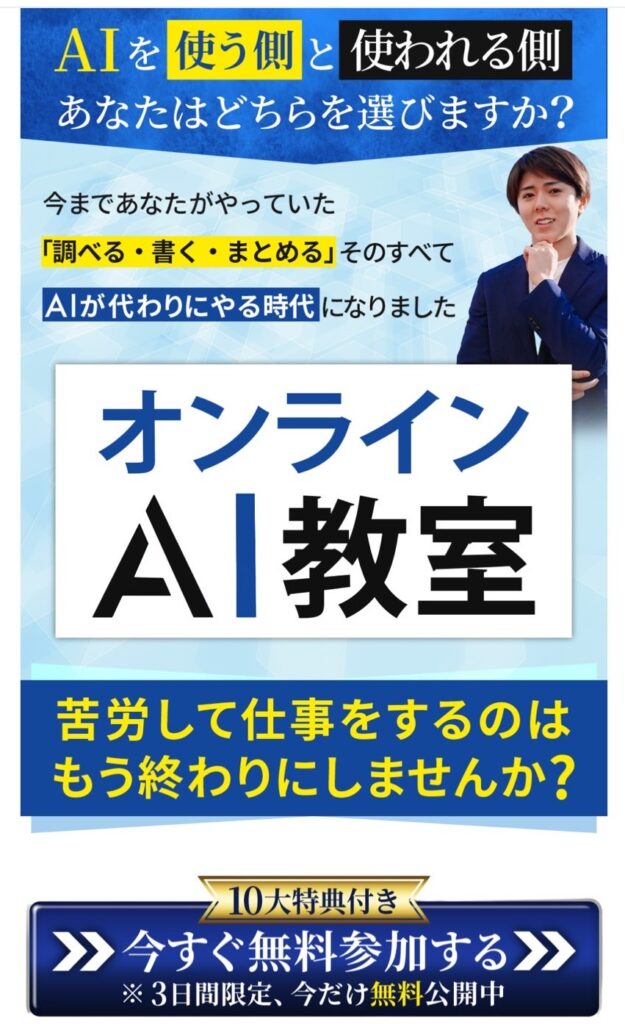
YouTubeで流れてきたAI ONEの広告が気になり、試しにLINE登録してみました。
登録後は、代表・森谷和正氏からの動画や、事前に見ておくと役立つAI学習コンテンツが届き、無料とは思えないほどの充実度でした。
オンライン教室では、スクールの紹介にとどまらず、最新のAI事情や日常での活用例まで幅広く学べて、とても濃い1時間でした。
ChatGPTや画像生成AIの使い方もわかりやすく解説されていて、「これなら自分にもできそう」と前向きな気持ちになれました。
しかも、強引な勧誘は一切なく「興味があればどうぞ」というスタンスだったのも安心ポイントです。
教室で教えてもらったプロンプトを使って、実際に作ってみた動画がこちらです。

まるで本物のチワワみたいですよね?自分でもこんな動画が作れるなんて、クオリティの高さにびっくりしました。
まとめ|AI ONEがきもいと感じた人こそ冷静な判断を

AI ONEの広告を見て「ちょっときもいかも」と感じる人は多いかもしれません。
でも、その印象だけで判断してしまうのは少しもったいないように思います。
実際に中身を見てみると、AIの使い方が身近な例で紹介されていたり、サポートがしっかりしていたりと、意外と実用的な内容が多くあります。
広告のインパクトには「目に留めてもらう」という狙いがあることも知っておきたいポイントです。
また、代表の森谷和正氏自身も、過去の発信をふり返り、現在は伝え方を変えている様子も見受けられます。
だからこそ、先入観だけで決めつけず、自分の目で確かめてみることが大切です。
- 広告が印象に残るのは、あえて強めに見せているため
- 運営会社や講師に怪しい情報は見つからなかった
- サポート体制が手厚く、学びの継続もしやすい
- YouTubeでは初心者向けに、日常で使えるAI活用例を紹介
- LINE登録の体験は内容が充実していて、しつこい勧誘もなかった
まずは、自分に合うかどうか、実際に見て判断してみるのがいちばんです。
もし迷っているなら、AI ONEの公式ブログをのぞいてみるのもおすすめです。
無料で読める記事の中にも、AI活用のヒントになる情報がたくさん詰まっていますよ。
また、代表・森谷和正さんについてもっと詳しく知りたい方は、経歴や発信の変化、人柄を紹介した以下の記事も参考になります。
広告では伝わりにくい“人となり”を知る手がかりになるかもしれません。